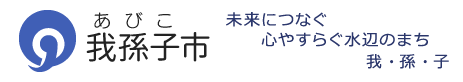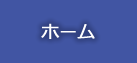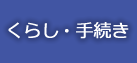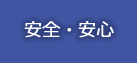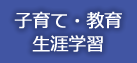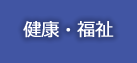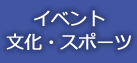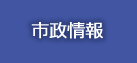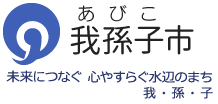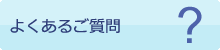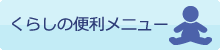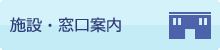令和7年度教育行政施策
令和7年度の教育行政の施策について申し上げます。
教育委員会では、教育施策の実現と生涯学習推進計画の更なる進展のため、令和6年度からの4年間を計画期間とする我孫子市第3期教育振興基本計画を策定しました。令和7年度は、引き続き、我孫子市第3期教育振興基本計画に位置づけた施策を着実に推進し、魅力ある教育と学習環境の充実を図ります。
令和7年度の教育施策の基本方針を「個性を尊重し、互いに学び合う、学校教育並びに生涯学習の推進」とし、施策を展開していきます。
第一の基本目標は、「確かな学力と豊かな心、健やかな体を育み、子ども一人ひとりがいきいきと輝く魅力ある学校づくりの推進」です。
一つ目の重点は、「学校教育環境の充実」です。
はじめに、安心して快適に学べる教育・学習環境の充実です。
湖北小学校体育館は、昨年7月29日に隣家の火災により使用することができなくなり、現在、解体工事と新築のための設計を同時に実施し、できる限り早く新たな体育館を再建することができるように事業を進めています。
再建に当たりましては、依然として多くの方から励ましなどの温かいお言葉とともに御寄附をいただいております。この場をお借りして感謝申し上げます。誠にありがとうございます。
次に、老朽化した小中学校施設については、建築からの年数の経過により老朽化が進んでいることから、その安全確保のため、機能維持や建替えのための費用が増え続けることが見込まれています。今後も引き続き、我孫子市学校施設個別施設計画に基づき、予算の平準化とトータルコストの縮減を図りながら、計画的保全による施設の長寿命化対策を進めることで、児童生徒が快適で安心な学校生活が送れるよう、適切な維持管理を実施していきます。
次に、水泳指導の民間委託についてです。児童の泳力向上や熱中症対策、施設維持管理費との費用対効果などが期待できることから、令和3年度から順次委託化を進めてきました。令和7年度は、新たに我孫子第三小学校、新木小学校を追加し、全小学校の水泳指導を民間事業者へ委託する予定です。
次に、信頼される学校づくりの推進、教職員の意識高揚を図る職場環境づくりについてです。令和6年9月に「我孫子市小中学校職員の働き方改革推進プラン」、令和5年6月に「部活動の在り方に関するガイドライン」を一部改訂し、教職員の働き方改革推進に努めてきました。今後も児童生徒と向き合う時間を確保できるよう教職員の多忙化解消に努め、信頼される学校づくりに取り組んでいきます。
次に、布佐中学校区の学校の在り方についてです。令和6年7月4日の総合教育会議で、義務教育学校を布佐小学校の敷地に建てることなど、大枠について合意形成を図りました。今後は市長部局と連携し、詳細な整備内容について意見交換を行いながら、我孫子市初の義務教育学校としてより良いものとなるよう事業を進めていきます。
二つ目の重点は、「子どもがいきいきと輝く学校づくり」です。
まず、確かな学力の育成です。学校におけるICTの効果的な活用については、引き続き、タブレット型端末を活用した学習や情報モラル教育を進め、児童生徒の発達段階に応じた情報活用能力の育成に取り組んでいきます。二学期が始まる令和7年9月1日から第2次教育ICTとして、新たに児童生徒に一人一台配付するタブレット型端末と学習支援ソフトウェアを活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図っていきます。また、新たに導入する校務支援システムを活用し、教育データ利活用や校務DXによる働き方改革を進め、組織的かつきめ細かな児童生徒への指導を実現していきます。
次に、幼児教育と小学校教育との連携・小中一貫教育の推進です。幼児教育と学校教育の接続を重視した幼保小連携の推進については、「我孫子市幼保小連携・接続カリキュラム」を通じて、幼稚園、保育園、認定こども園と小学校の交流活動や目指す子どもの姿を共有しながら、育ちや学びの接続を図っていきます。
小中一貫教育の推進については、平成25年度から「小中一貫教育の研究・推進」に取り組み、平成31年度から全ての中学校区で小中一貫教育を実施しています。令和4年度より教育委員会から任命された保護者や地域住民の方々が、一定の権限と責任を持って学校運営に参画する仕組みとして、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)がスタートし、市内全小中学校に学校運営協議会を設置しています。学校運営協議会が承認した中学校区ごとの小中一貫教育基本方針に基づいて、学校運営を行っていきます。
また、小中一貫教育とコミュニティ・スクールの一体的推進を目指し、学校と地域住民が連携して活動しています。令和6年度は、各中学校区で小中学校9年間の一貫したテーマを決め、地域の特色を生かしたオリジナルカリキュラムを作成しました。令和7年度は、作成したカリキュラムを確認、修正しながら実施していきます。
続いて、地域とともにある学校づくりです。コミュニティ・スクールを通して、学校と地域が子育ての目標やビジョンを共有し、パートナーとして連携・協働を図ることで、地域に根ざした教育の充実を目指します。また、子どもたちの未来を育む豊かな体験活動を充実させるため、市内全小中学校に地域学校協働本部を置き、地域学校協働活動推進員を配置し、地域の自然環境や教育資源の積極的な活用を図るよう努めています。子どもたちの学びや活動を一体的に支援するためにも社会教育団体を含めたボランティアネットワークを構築するとともに、学校と地域の双方向から連携・協働できる体制の整備をさらに推進していきます。
中学校の部活動については、少子化対策や教職員の働き方改革等、さまざまな課題を踏まえ、生徒がスポーツや文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保できるよう、休日部活動の地域移行を進めていきます。
令和6年度に国・県から委託される実証事業として、白山中学校の一部の部活動で休日地域クラブ活動を実施しました。令和7年9月より、この実証事業を市内全中学校に拡大し、各校1部活動以上で実施します。令和8年度以降の部活動地域移行の本格実施に備え、子どもたちの様々な体験と学びの場を確保していきます。
次に、長期欠席児童生徒対策事業の強化です。不登校児童生徒への対応は、喫緊の課題です。個々の状況は異なるため、支援に当たっては、児童生徒と保護者の意向を確認し、実態に合った教育を支援していく必要があります。
校内教育支援センターは、登校できるが、在籍する学級での教育活動に参加することが難しい児童生徒が利用しています。なかには、在籍する学級と行き来する子や、教室復帰を果たした児童生徒もいます。
現在校内教育支援センターは、全中学校6校、小学校8校、計14校に設置されています。令和7年度中には、市内19校全てに設置し、不登校対策の核となるべく、校内教育支援センターコーディネーター・指導員の確保に努め、子どもたちの学びの機会を広げていきたいと考えています。
引き続き、心の教室相談員やスクールソーシャルワーカー等、専門スタッフによる学校のサポート体制を強化し、学校が原因となる長期欠席児童生徒の解消に取り組んでいきます。
次に、いじめ・非行防止対策です。いじめは絶対に許されない行為であり、どの子どもにも、どの学校においても起こり得るものであることを十分認識するとともに、集団の中で子どもたちがお互いの個性を認め合えるよう継続的に指導しています。
いじめの防止及び早期発見・早期解決を図るため、年2回の「我孫子市いじめについてのアンケート」と小学校3年生から中学校3年生までを対象とした「WEBQU(子どもたちの学校生活における満足度と意欲、学級集団の状態を調べることができるアンケート)」を実施しています。アンケート結果を基に、指導主事や教育相談センター職員などを学校に派遣し、児童生徒の観察や学校へのアドバイスを行っています。児童生徒や保護者から寄せられるさまざまな悩みに寄り添うとともに、全ての児童生徒が安心して生活し、健やかに成長することができるよう、環境整備に向けた検証と改善を行っていきます。
非行防止対策については、少年指導員、防犯協議会などと協力し、不審者情報の発信や街頭パトロール等、非行防止活動に取り組んでいます。また、問題解決に向けて迅速に対応するため、引き続き警察と連携していきます。
三つ目の重点は、「子どもの成長に応じた発達への支援」です。
一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援体制の構築と教育相談・支援体制の充実を図ります。
帰国・外国人児童生徒への支援体制の整備については、引き続き、令和7年度も対象児童生徒に対する通訳の派遣や日本語指導等の支援体制を推進していきます。
また、言語聴覚士の学校巡回により、ことばやきこえに心配のあるお子さんを支援していきます。
次に、特別支援教育の推進についてです。教育相談センターでは、特別な配慮を必要とする就学予定の児童生徒に対し、適正な就学の支援を行うため、本人の状態、保護者の意向や学校の状況、医師や心理学等専門的見地からの意見を踏まえ、教育支援委員会を中心に総合的な観点から就学先を決定しています。
就学後においても一貫した支援を行うため、児童生徒一人ひとりに合わせた個別の教育支援計画・個別の指導計画等を作成するとともに、特別支援教育アドバイザーを配置し、引き続き、学校全体で支援体制の強化を図っていきます。
なお、その他事項として、学校給食管理運営事業についてです。
これまで国からの交付金を活用して値上げの抑制に努めてきたところですが、令和7年度以降の交付金の見通しが立っていないことから、令和7年4月以降の学校給食費を小学校は1食60円、中学校は1食90円の値上げを行います。しかし、これまで実施してきた第3子以降無償化及び市独自の第1子・第2子への月額1,000円の支援金給付、準要保護児童生徒への就学援助制度については継続し、引き続き負担軽減策を図りながら、安心・安全な給食を提供していきます。
第二の基本目標は、「市民が地域の自然や文化に愛着を持ち、豊かな人生を送ることができる環境づくりの推進」です。
一つ目の重点は、「生涯学習環境の充実」です。
学びたいときに学べる学習機会の充実を図るとともに、人づくり・まちづくりにつながる学習活動を支援していきます。また、公民館、鳥の博物館、図書館などの学習施設について整備と充実に取り組んでいきます。
図書館では、利用促進のため、めるへん文庫基金を活用し、現在運行している移動図書館そよかぜ号よりも小さい軽自動車タイプの移動図書館車両を購入し、令和8年1月から運行を開始する予定です。現在の移動図書館車の大きさでは通れなかった狭い道にも入ることができ、図書館サービスが届きづらかった地域にも本を届けることができます。図書館がない地域や保育園・幼稚園、子ども向けのイベント等への運行を視野に、小型で高い機動力を活かして読書活動を推進していきます。
また、令和6年度に導入した電子図書館サービスのさらなる活用を進めるとともに、関係各課と連携し、歴史・文化資料のデジタルアーカイブ化による郷土学習を推進していきます。
二つ目の重点は、「歴史文化財の保存・継承と文化の振興」です。
文化芸術活動への支援と環境整備については、市民文化団体との連携を図り、市民の自主的な文化芸術活動を支援していきます。伝統文化や郷土芸能を次世代へ継承するため、体験を通じて文化を身近に感じてもらい、興味を持つ入口となるよう「みんなの文化体験会」や「郷土芸能体験教室」を継続的に実施していきます。また、文化祭・音楽コンサート等、市民が文化芸術活動に積極的に参加できるよう活動や発表の場を提供するとともに、舞台鑑賞事業等を通して、子どもたちが舞台芸術に触れる機会の充実を図り、文化芸術活動が発展していくための環境を整備していきます。
歴史的・文化的遺産の整備・活用では、「我孫子市文化財保存活用地域計画」に基づき、旧井上家住宅や白樺文学館、志賀直哉邸跡書斎、杉村楚人冠記念館など市内の史跡や文化財により親しみを持っていただけるよう保存活用を進めていきます。
埋蔵文化財や歴史資料の調査・研究では、市内に所蔵されている古文書や民具などの資料調査を進め、データベースとして順次公開し、調べ学習の機会を増やせるよう活用できる仕組みを整備します。
また、令和6年度より、我孫子市文化財ボランティア養成講座を受講・修了された方を我孫子市文化財ボランティア名簿に登載しています。文化財施設のガイドボランティアや資料調査ボランティアを通して、イベントや展示解説にご協力いただき、文化財施設のさらなる魅力アップを図っていきます。
三つ目の重点は、「スポーツの振興」です。
生涯スポーツの推進では、「我孫子市スポーツ推進計画」に基づき、スポーツ推進委員等と連携し、7つの総合型地域スポーツクラブの育成と支援を行うとともに、生涯スポーツを支えるスポーツ指導者の養成に努めます。
スポーツを楽しむ機会の充実では、初心者から上級者まで、年齢を問わず一緒に楽しめるランニングイベント「手賀沼チームラン・キッズラン うなきちカップ」をはじめ、ファミリースポーツテスト、ボールゲームフェスタ等、スポーツに親しめる機会の創出に努めていきます。
以上、教育委員会の施策について申し上げましたが、事業の推進に当たり、議員の皆様・市民の皆様の一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。